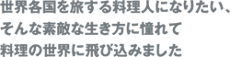
私はイタリアの小さな村で生まれ育ちました。そして幼い頃から料理が大好きだった。
料理人になろうと決心したのは13歳の時。料理をやりたかったというのもあるけれど、一番の理由は海外を飛び回りたかったから。
生家の隣に住むご主人はいつも長期不在で、時折顔を見せてはまた海外に出かけてしまうような人でした。聞くところによると、包丁ひとつでロンドンやヴェニスなど、国境をまたいでレストランを旅する料理人なのだとか。ボンボヤージュ! 旅する料理人。
彼の生き方に憧れ、私も世界各国を旅する料理人になりたいと思ったのです。料理はどこの国でも必要とされるもので、誰もが毎日食べることを考える。何より、その時の自分にとって料理以上に好きなことはなかった。
さっそく15歳で家を出、まずは北イタリアの二ツ星レストランに入りました。同じイタリア内でもこの店の料理はフレンチの息吹が十分に感じられ、まずその違いに驚愕しました。伝統的なイタリアの地方料理で育った私にとって、それはまるで別ジャンルの料理。レシピはあるものの、こちらが嫉妬するほど自由奔放に作り手が自分を表現していました。
この店のシェフはフランスで修行をした経験があり「もっといい方法はないか」と常にポジティブで、新しい発想が湧き出るたびに嬉々としていました。そんな彼を崇拝し、私の中には“渡仏”という道しるべが見えはじめていきました。
その後は、念願のフランスをはじめ、ロンドン、ニューヨークなど世界各国を渡りました。どの店でも強く感じたのは“すばらしい料理は強い団結力から生まれる”ということ。例えばモナコのレストランでは、キッチンに14カ国のスタッフが集結していました。フランス人、アメリカ人、日本人…、国籍を超えて彼らは一致団結し、秀逸なる一品を生み出す。執念にも似た彼らの意気込みに圧倒されたのです。
その店には世界中から厳選された食材が毎日届きました。料理人としてはこの上ない贅沢でした。にもかかわらず「どんなにすばらしい食材をもってしても、チームワークの力に勝るものはない」と確信するほどでした。
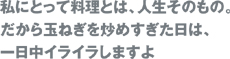
さて、そんなことを感じながら、私は一流を目指して邁進しました。ニューヨークにいる時は、雑誌などでも活躍していたカリスマ料理人アラン・デュカス氏の本なども読み、彼のようになりたいと想いを膨らませました。そして2000年、私が24歳の時、幸運にもデュカス氏と出会い、彼の下で働くことになったのです。晴天の霹靂でした。
デュカス氏にとって、料理に対する情熱は彼の命脈になっていると思います。また非常に繊細な一面もある人です。現在、彼は約25のオーベルジュやレストランを展開していますが、いまだに彼はいち料理人として食材や味の開発に余念がありません。
彼は店をコピーすることを好まず、「ブノワ」に対しても日本の「ブノワ」はここだけだからと言い、レモンを添える位置まで一緒にアイディアを出してくれます。不動の地位を築き、グランシェフと呼ばれるようになってからもなお、子供のように瞳を輝かせ、好奇心旺盛に料理を追及しているのです。
8年間デュカス氏の下で働き、「ルイ・キャーンズ」(モナコ)、「ベージュ アラン・デュカス 東京」(日本)など、私は世界のデュカス・グループのレストランを数多く経験しました。オーセンティック、コンテンポラリー、クラッシック、ビストロなど、そのスタイルはさまざまですが、共通しているのはどこのスタッフも私のようにデュカス氏を尊敬していることです。
私にとって料理とは、人生そのもの。だからちょっとでも玉ねぎを炒めすぎた日は、何となく一日中イライラします(笑)。料理人なら分かるでしょ?この気持ち。それでも日本は癒しの国だからまだ救われている方かもしれません。しかも日本人はみんな勤勉です。ひとつ料理を伝授するとまったく同じように毎回完璧に上げてきてくれます。食材も業者さんが箱にきれいに並べて持ってきてくれます。下の方の食材がつぶれていた、なんてこと、よその国では日常茶飯事です(笑)。
料理人の仕事は未来永劫、ロボットにはできない貴重な営みだと思います。溢れ出るパッションを表現する作業ですからね。人間だけが成せる業なのです。だからこれからもいろんな国を回って、新しい発見をしてみたい。でも肝心なことは、どこにいるかではなく、料理ができるかどうか。たとえどんなに狭いキッチンでも、僕にとっては料理すること自体が至福の喜びなのだから。



