
第161回 株式会社外食文化研究所 代表取締役社長 水口憲治氏
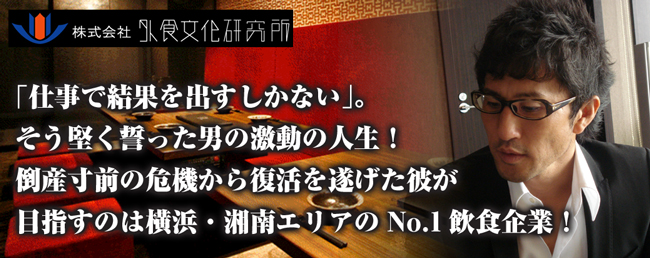

| 株式会社外食文化研究所 代表取締役社長 水口憲治氏 | |
| 生年月日 | 1968年4月30日生まれ。 |
| プロフィール | 大手ゼネコン会社に勤める父と専業主婦であった母の次男として生まれ、幼少期は大阪で過ごす。7歳のとき、父の仕事の都合で埼玉へ転居。中学の頃はサッカー部に所属していたが、高校入学とともにバイトと遊びに明け暮れる。2年生で高校を中退し、インテリアデザインを学ぶ。デザイナーでの独立を志していたが、飲食の世界で起業することを決意し、27歳で独立。商品・サービス・空間の三位一体で勝負するオンリーワンダイニングを目指し、横浜・湘南エリアで「いち稟」「プクプク」「うる虎」といった業態を展開。2009年からは1年に1人を独立させる独立支援事業も開始した。 |
| 主な業態 | 「いち稟」「プクプク」「うる虎」 |
| 企業HP | http://www.gaishokubunka.com/ |
勉強もスポーツもダメ。仕事を頑張るしかなかった。
「兄へのコンプレックスがそもそもの始まりだったかもしれませんね」。株式会社外食文化研究所の社長、水口はこう語る。寡黙で勤勉。そして大手一流企業へ就職した5つ上の兄。一方、部活も入らず、バイトに明け暮れ、稼いだお金で当時のブームであったDCブランドを買い漁る高校生活を過ごした水口。しまいには2年生の時に退学。親からも呆れられていたという。その後、通信教育で高校課程を修了したものの、「勉強もスポーツも人には勝てない。がむしゃらに働くしかない」と大学には行かず、引越し、土木、飲食など様々なアルバイトを経験。とにかく必死に働いた。その姿が評価されたのか、ほとんどの職場で「社員にならないか?」と誘いを受けた。理由を聞くと、「良い人材は手放したくないからだ」と返ってきた。勉強ができなくても、スポーツができなくても、一生懸命仕事をすれば認めてもらえる。水口の中に、“働く楽しさ”が芽生えていった瞬間であった。と同時に、「自分の力でメシを食っていける仕事はないだろうか」と考え始めるようになった。
クリエイティブの世界から飲食の世界へ。
19歳のとき、ある転機が訪れた。飲食店のオープニングスタッフとして入った水口は、開店前にやってきたその店舗担当のインテリアデザイナーの姿に目を奪われた。白髪で、60歳近いにも関わらず、なんとも表現しがたいカッコよさが漂っている。「衝撃的だった。こういう大人になりたいと思った」。その瞬間、水口はインテリアデザイナーになることを決意。アルバイトとかけもちしながら夜間の専門学校に通い、24歳のとき、代官山の有名なデザイン事務所に就職した。ここでも水口は、必死に働いた。徹夜や泊まり込みは当たり前。家に帰るのは週1日ぐらい。深夜3時から打合せが行なわれることもあったという。そんな生活サイクルを余儀なくされていたため、同僚は続々と体を壊し、退職。気づけば水口は、経営者の右腕的ポジションになっていた。仕事の多くは、飲食店のインテリアデザイン。多くのオーナーと向き合いながら、繁盛店をつくるにはどうすればいいか、を日々考えていた。そんな毎日を送るにつれ、入社当初の「30歳までにデザイナーで独立したい」という夢が、次第に「飲食で独立したい」に変わっていった。そして26歳のとき。デザイナーでの成功が見えていたものの、3年勤めた会社を退職。飲食への第一歩を踏み出すこととなった。
焼き鳥チェーンのFCに加盟。繁盛店を作った末に、独立。
しかし、過去のアルバイトやデザイン会社での経験から、店舗オペレーションはなんとなくは分かるものの、料理が作れるわけでもなく修業をしている暇もない。ましてや店を作る資金もない。そんな状況の中で水口が最初に選んだのは、イニシャルコストを抑えられ、料理のマニュアルや素材も提供してもらえる焼き鳥チェーンのFC加盟だった。オーナーとして店舗経営を行なう前に、チェーン内でも売上TOPの模範店での研修がある。3ヶ月間、水口はその店舗に勤務したのだが、想像を超える繁盛ぶりに、「間違いなく儲かる」と自信を深めたという。ところが研修を終え、いよいよ迎えた水口の店のOPEN初日、自分が抱いたイメージとは大きくかけ離れた現実が待っていた。まったく客が入らないのだ。「夢が打ち砕かれた想いでした」。水口は語る。だが、そうは言ってもやるしかない。水口は1日も休むことなく必死で働き続けた。できることは何でもした。結果、初月は130万円の売上。なんとか黒字を出すことに成功した。とはいえ、休みゼロでやっと出せた数字。今後もこれを続けていくのは無理がある。そう考えた水口は、徹底的に挨拶・掃除・時間管理という飲食業における“当たり前”のレベルを上げていった。すると、半年後には月商200万円超え、1年後には行列ができる超繁盛店へと進化していったのだ。そして2年間のFC契約が満了。いわゆる雇われオーナーを卒業した水口は、1997年、晴れて初めてのオリジナル店「いち稟」をOPEN。その2年後に株式会社外食文化研究所を設立した。
どん底からの奇跡の生還。信頼できる仲間たちとNo.1企業を目指す。
会社は順調に伸びていった。人材も育ち、念願だったデザイナーズBarをはじめ店舗数も着実に増やしていった。ただ1度だけ、水口自身も「会社が潰れてもおかしくなかった」と語る大きな分岐点があった。それは2004年のこと。「FC展開も視野に入れたい」と考えた水口は、そのノウハウを得るためにも1度どこかのFCに加盟しようと目論んだ。社員はみんな揃って反対した。しかし、これまでの成功体験から天狗になっていたのだろう。ワンマン経営者のごとく、周囲の声に耳を傾けることなく行動に移した。ところが、これが完全に裏目に出た。まったく売上が上がらない。銀行への返済額を含めると毎月450万円の赤字。それまでの好業績がウソだったかのように、会社が一気に崩れだした。いよいよ資金は底をつき、担当の税理士からは「会社をたたむ準備を始めてください」と言われた。この危機的現状を、社員たちに説明すべきか水口は悩んだ。原因は自分の身勝手な行動。話をすれば、間違いなく全員辞めていくだろう。しかし、時間の問題だ。意を決し、水口はすべてを打ち明けた。社員に頭を下げたのも、初めてのことだった。すると、意外な反応が返ってきた。「僕たちをここまで育ててくれたのは、すべて社長のおかげ。次は僕たちが社長に恩返しをする番です」と。その言葉を聞き、水口は目が覚めた。弱気になっていた自分を恥ずかしく思い、「絶対に会社を潰すわけにはいかない」と堅く心に誓った。すぐにFC契約を解き、多額の違約金も支払った。お金なら銀行に頭をこすりつけてでも借りればいい。すべては会社を存続するため。当然、借金は大きく膨れ上がった。しかし、社員たちとの絆はこれまで以上に深まった。その結果、直営店の売上が急激に伸び始め、どん底にあった会社は奇跡の復活を遂げたのだった。水口は語る。「横浜と湘南を拠点にする飲食企業はたくさんありますが、その中で、店舗数・メディアへの露出・グルメサイトなど、何でもいいから多くのNo.1を勝ち取る。これが今の目標。みんなと決めた目標です」。水口には心から信頼しあえる仲間がいる。固い絆で結ばれた彼らなら、横浜といわず全国No.1の飲食企業にもなれるのではないかと思えてしまうのが不思議だ。
思い出のアルバム
 |
 |
 |
この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方
この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます。
例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい、中学時代の同級生だった など
