
第304回 株式会社加寿翁コーポレーション 代表取締役社長 竹内太一氏
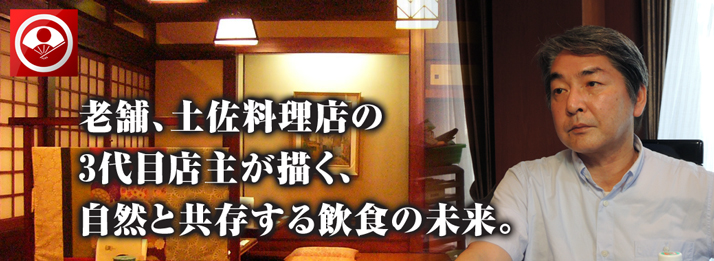

| 株式会社加寿翁コーポレーション 代表取締役社長 竹内太一氏 | |
| 生年月日 | 1953年8月18日 |
| プロフィール | 高知県高知市に生まれる。大正6年創業の老舗料理店3代目の誕生である。兄弟は姉と妹。明治大学卒後、父が経営する会社に入社。社長就任後、仕入れや物流の見直しなどに取り組み、土佐料理「司」・「祢保希」のブランド化を一層推進する。1995年には、「鰹のたたき」の宅配事業を開始。1997年には「ゆずぽん酢」を商品化し、量販店などへの出荷もスタートさせている。現在、「祢保希」を東京都内に5店舗、「司」を大阪・高知に6店舗、酔鯨亭を大阪・高知に各1店舗ずつ出店。食品事業にて海外進出も模索している。 |
| 主な業態 | 「祢保希(ねぼけ)」「司」「酔鯨亭」 |
| 企業HP | http://www.kazuoh.com/ |
父、和夫氏が「土佐料理」と命名。
名前にはちからが宿ると言ったのは、平安時代の陰陽師、安部清明だっただろうか。
高知県の郷土料理を「土佐料理」と命名することで、いまで言うブランド化を図り推進したのは、今回ご登場いただく株式会社加寿翁コーポレーションの現社長、竹内太一の父、和夫氏である。昭和中期から和夫氏が展開した「司」や「祢保希」が高知県の郷土料理の代表格となったのも頷ける話だ。
和夫氏が、創業者である竹内の祖父小松牛次氏に養子として迎えられたのは、竹内が生まれる1年前の話。竹内が生まれた翌年には、高知にて中華料理店を開業している。
祖父の小松牛次氏は高級料亭に勤める腕の立つ板前だった。その腕を活かし、大正6年に「新京橋ねぼけ」を創業する。「大衆化したことでヒットした」そうだ。
父の和夫氏が「土佐料理 司」を高知市はりまや町に開店したのは1964年のこと。そののち「土佐料理 司」は高知県でも名店として知られるようになる。
この名店と歩みを合わせるように、竹内もまた成長していく。中学から中・高一貫の進学校に入り、中学では軟式テニス部、高校では水泳部に籍を置いた。「街には城もあって、街全体が遊び場だった」という。当時のセリの話も伺った。「高知県の市場にはたくさんの種類の魚が出回っていました。セリの時には、セリの順番を待つ鰹船がズラリと港にならんでいたものです」。
最近は高知でも漁獲量が落ちてきたそうだ。豪快な一本釣りも姿を消しつつあるらしい。にぎやかな時代の話と対照的に、さみしくも思える話である。
土佐料理、大阪へ。
高校を卒業した竹内は、東京の大学に進学しようと心に決めた。独り暮らしに対する憧憬があったかもしれないが、その話を両親にすると「家族全員で」という返事が返ってきた。竹内が18歳といえば、1971年の話である。
その1年前の1970年には、日本で初の万国博覧会が大阪府吹田市で開催されている。さらにその前年1969年には日本で初めての地下街、水の流れる街「阪急三番街」がオープンする。「司」は、そこに出店した。
すでに高校生になっていた竹内は当時のことを鮮明に覚えている。
「偶然、高知新聞に載ったテナント募集の広告を父が観たんです。もちろん、錚々たるお店が応募するのだろうから、ダメモトという気持ちもあったと思います。予想通り、一度は採用してもらえなかったんですが、たまたま空きが出て声をかけてくださったんです」。17坪の小さな店だった。それでも二つ返事で快諾した。土佐料理店の大阪、初出店である。
17坪の店で、赤坂を買う。
「夏休みになると駆りだされた」と竹内は笑う。友人も誘った。その間は、従業員たちと同じ寮に住む。バイト先は言うまでもなく、三番街にある「司」である。竹内曰く「気絶するぐらい忙しかった」そうだ。
「たった17坪でしょ。しかも、当時は鰹のたたきが、200円です。それでも月商1500万円ぐらいになったんですから、どれだけキリキリ舞いだったか想像いただけると思います」。立地も良かった。万国博覧会が開催されたことも幸運だった。しかも、1968年にはNHK大河ドラマ第6作として「竜馬がゆく」が放映されている。3つのことが重なり、「司」は爆発的な売上を記録する。
毎日、土佐からトラックで「鰹」を配送してきます。いまでは4時間ぐらいですが、当時は6〜7時間はかかった。ある時期から飛行機を使いますが、当時は自社でトラックを走らせていました。「いいものを安く、おいしく」。食材に、こだわりに抜いたことも、味にうるさい大阪で成功した秘訣なのではないだろうか。
「この17坪の店の利益で、赤坂の土地を買った」と竹内。
竹内の大学進学と共に竹内家は東京に移住するが、その原資を生み出したのが、この「三番街の司」である。万国博覧会を境に、日本は高度成長期に突入する。
東京進出。竹内は、明治大学、ヨット部へ。
新聞記者になりたかったそうだ。「もともとは東京へとは思っていなくって、同志社大学へ行きたかったんです。でも、相手がどうも受け入れてくれなくってね」とこちらを笑わせる。「日大と専修には歓迎されたんですが、イヤだといって1年浪人しました。その時にはすでに『家族で、東京に行く』ことになっていましたから、親父からは怒られましたね。それでも我を通して、1年後に明治に入学しました」。竹内の頑なないちめんが伺える話である。
赤坂に買った土地に自社ビルを建て土佐料理「祢保希」を出店したのは1972年。家族は高知にいた頃とおなじように、店の最上階で寝起きした。
ただし、この「祢保希」は、いままでの店のようにうまくいかなかったようだ。
「料亭街だということもあったんでしょう。1年ぐらいは鳴かず飛ばず。私も学業のかたわらで半年間ぐらいは街角でマッチを配っていました。それが、ある時マスコミが取り上げてくれたおかげでみなさんが認知してくださるようになったんです。個室もあって、使い勝手もいい、料理も旨いじゃないか、と。そういうことで、繁盛店になっていくんです。鰹の時期にTVが入ったのも、大きな宣伝になりました」。当時はいま以上にTVのちからは絶大だった。
地下1階、地上4階の200席。坪数はのべ300坪ある。この土佐料理「祢保希」は、都会人たちの旺盛な食欲を満たし、肥えた舌を魅了した。この赤坂店の成功は、のちの新宿、渋谷、銀座、丸の内などへの出店の足がかりとなる。ちなみに銀座店も、自社ビル。財務基盤も確立されていった。
ところで、店が増えていく一方で、竹内の学業はどうだったのだろう。「海が好きで、ヨット部に入っていました。ヨットですから、海じゃないと練習もできないでしょ。だから、200日は海で合宿です。引き算すればわかりますが、学校にはほとんど行っていません。それでも、無事、卒業できたのは大学紛争があったからでしょうね。普通だったら、学校も卒業を認めてくれなかったんじゃないかなぁ」。
真っ黒に日焼けした竹内の顔が想像できる。荒波に揉まれ、いつのまにか逞しくなったその体躯も。
大手コンピュータ会社より父の会社。息子の選択。
大学を卒業すると就職が待っている。老舗3代目にしても、おなじ。竹内は外資の大手コンピュータ会社への就職が決まった。しかし、母の一言で、翻意を翻し、父の会社に入社することになった。母に従う、これが息子の選択だった。1976年のことである。
「入社当時から、仕入れも、将来を見越しての新卒採用にも取り組みました」。ただし、高知ではベスト3の頑固者で通っていた父の和夫氏とは衝突もあったはず。それでも店は繁盛し、出店を繰り返し、1986年には東京に本社ビルを置くまでになった。1990年には坂本龍馬記念館に1000万円を寄付。父の会社は、絶頂期を迎えた。ちなみに現在の株式会社加寿翁コーポレーションに社名を変更したのは、1992年のことである。一般的にバブルが弾けた年と言われている。
父から息子に経営が託されたのもこの時期である。「宴の後始末は子どもの仕事だと思った」と竹内。年商は40億円あったが、借金は35億円にものぼった。
それまでせっせと貸し付けた銀行が掌を返し、返済を迫ってくる。ゴルフ会員権など、売れるものはすべて売ったそうだ。「5000万円が0円になったこともある」という。損切した額だけで10億円にもなったそうだ。店の売り上げも下がる一方だった。
昔から付き合いのある銀行の頭取にも会いに行った。頭取は、竹内のやりかたを支持してくれた。社員たちも、支援してくれたことだろう。
「最悪だったが、これを潜り抜けることがオレに与えられた試練なんだ」と歯を食いしばった。すると大事なものもみえてきた。「銀座や赤坂に土地があったことが幸いしました」。父からは負の資産も受け継いだが、それを上回る資産も受け継いだことになる。
むろん「土佐料理」は、引き継いだなかで最大の資産だったに違いない。
「バブル期には、会席料理やしゃぶしゃぶ、串揚げなどいろいろな業態の店を出しましたが、いずれも失敗してしまいます。それで、改めて土佐料理という得意分野に注力することにしたんです」。
食材にこだわり、仕入れも見直した。産地へも自ら積極的に出向き、産直の朝どれ、天然ものを使用した。鮮度を保つため、輸送・物流ももちろん見直した。これらの工程を経て「土佐料理」はさらにブラッシュアップされていくことになる。同時に「土佐」の料理がより一層見直され、認知されることにもつながった。「土佐」すなわち高知県産の、鰹やゆずといった食材が持てはやされるようになるのである。
竹内流、土佐料理の展開。
土佐料理の認知度が再度、アップする。その流れに敏感に反応した。1995年には、高知市食品団地に食品流通センターを設置し、司ブランドの「鰹のたたき」の宅配事業を開始。1997年には、「ゆずぽん酢」を商品化し、量販店などへの出荷を開始する。
「店」と「商品」、この2つが、両輪となる。ちなみに「鰹のたたき」「ゆずぽん酢」も現在はネットでも販売されているので、気軽に購入することが可能だ。
「お店で信用を築き、売れ筋メニューを商品化する。それをネット事業が支える。こういう循環も出来つつある」とのことだ。「ゆずぽん酢」は、量販店にも出荷。業務用にも進出している。
その一方で、海外への出荷も検討中だ。「アジアをはじめ、各国の日本食ブームをみていると興味は注がれますが、海外に店はまだ出しません。代わりに『ゆずぽん酢』などの食品事業で海外進出を検討しています。台湾への出荷が最初になりそうです。パリで行われる食品の展示会にも出品します。ゆずというフレーバーはまだ向こうにはない。おもしろい展開ができそうです」と竹内。
眼は海外に向いている。ただし、そのためには、まだまだ強化していかなければならないことが多い。その一つに世代交代を挙げている。2017年に100周年を迎える歴史があるうえ、定着率が高いだけに、平均年齢も高止まりしたまま。新卒採用にも注力してきたが、年齢層でいえば20代が少ないのが目立つ。世代交代を進めることで、一気に年齢構成を平準化したい考えだ。
収益性を高め、財務体質を強化するのも目標の一つだ。むろん前述した「食品事業」は、今後のカギを握っている。
そのなかでも、人材の育成は、竹内がもっとも注力したい点。国内はもちろん海外でも通用する人材の発掘と育成が急がれている。「人を育てる仕組みづくりが課題」ということだ。
土佐に貢献。一次産業の復興に携わる。
竹内は企業の発展とともに、「土佐」に対する恩返しも行っている。たとえば、2010年度の「優良外食産業表彰」において、加寿翁コーポレーションは、最高位の農林水産大臣賞に選ばれているのだが、中身は、「土佐はちん地鶏」などを活用したメニュー「龍馬鶏」、国内有数の生産高を誇る「ゆず」を使ったぽん酢、刺身用鮮魚の物流ルートの開発などが評価されてのこと。いずれも、高知の一次産業との関わりがテーマになっている。
仁淀川の天然鮎が減少していることを受け、2008年に高知県と、いの町・仁淀川流域の森林を協定森林とする「協働の森づくり事業」パートナーズを協定。同町の町有林44ヘクタールに「鮎を育む森」と名付けて森林整備を行っている。
ほかにも、鰹などの乱獲に対する警鐘を鳴らし情報を発信、高知県のエネルギーの循環社会への取り組みにも精力的にかかわっている。
高知あっての土佐料理といえばそれまでだが、竹内の取り組みは決してそれだけでは説明できないように思う。利己的な発想を超えた、「自然との共存」というテーマが根底に流れている気がするからだ。
今後の外食を描こうとする時、この「自然との共存」は避けて通れないモチーフだろう。その絵をどう描いていくのか、まだまだ竹内の手腕に期待したいところである。
思い出のアルバム
 |
 |
 |
| Tweet |
この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方
この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます(すべての取材先企業様、代表の方に連絡が取れるわけではありません。こちらから連絡がつく場合に限ります)。
例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい など
