

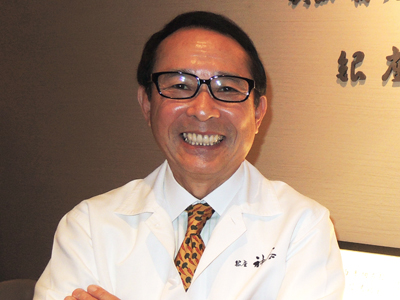
| 有限会社竹がみ 主人 神谷昌孝氏 | |
| 生年月日 | 1947年10月7日 |
| プロフィール | 愛知県幡豆郡幡豆町(現在の西尾市)に生まれる。15歳で料理の道に進み、名古屋の奥座敷といわれた渓谷・定光寺の「千歳櫻」で修業を開始。老舗料亭赤坂「きくみ」の料理長就任を経て、独立。現在、都内に4店舗の料理店を構えている。和食の基礎を大切にしながら、料理のジャンルを超えてより良い技法と食材を探し求めている。 |
| 主な業態 | 「日本料理 神谷」「たけがみ 一轍そば」 |
| 企業HP | http://www.kamiya-m.com/ |
今回は、日本料理を代表するお一人、「竹がみ」の主人、神谷昌孝氏に話を伺った。
料理人に憧れて。
「パーマの実験台になったこともある」と言って、神谷は子どもの頃を振り返る。父親が理髪店を営んでおり、子どもの頃は父親から「散髪屋になれ」と言われたこともあるそうだ。父親は逆らえない存在で、スパルタだったと笑う。
神谷は戦後間もなくの1947年、北側には愛宕山を仰ぎ、南側には三河湾を望む、山にも海にも囲まれた風光明媚な町、愛知県幡豆郡幡豆町(現在の西尾市)に生まれている。男4人、女3人の7人兄弟の4男坊。ともかく、わんぱくだったらしい。
「おかげで、うちの散髪屋には子どもが誰も来ないんです」と言って笑う。小学校に上がってからはガキ大将になった。野球部に所属。成績は、「まぁ、そこそこ」だったそうである。
中学に上がってからは、テニス部に所属。「試合で負けなし」というのだから、巧かったのだろう。一方、海に行ってはカニを獲ったり、ナマコを獲ったりしていたそうである。
料理に関心を持ったのは、親戚の家に遊びに行ったことがきっかけ。
「叔母が食堂をやっていまして、夏休みに遊びに行くと親子丼などいろいろなものを食べさせてくれたんです。板前さんもいて『かっこいいな』と思ったのが料理に興味を抱くきっかけです」。
中学を卒業する頃になると、父から「散髪屋に修業に行け」と言われる。しかし、その時にははっきりと「料理人という職業を意識するようになっていた」そうだ。
だから、神谷は高校に進学せず、「料理人になるべく修業を始めよう」という選択をする。15歳の、決断だった。
15歳。料理の道に進む。
神谷が15歳といえばまだ1962年のことである。当時の板前修業とは?
当時の話も伺った。
「私は、名古屋の奥座敷といわれた渓谷・定光寺の「千歳櫻」で働き始めます。200人はいる大きな旅館です。もちろん今と比較することはできません…」、そう断ってから神谷は当時の話をしてくれた。
「料理人は、裸足のままなんです。これがきつかった。大きな旅館だったものですから、夜中の2時まで洗い物です。足は全部霜焼けで痛い思いもしました。先輩は任侠のような人ばかりで(笑)」。
ガキ大将だったはずの神谷も、さすがに厳しい先輩たちが部下を叱責する様子には息を呑んだことだろうと思っていたが、神谷にとっては、そう怖い存在でもなかったらしい。
「私は、一番小さかったということもあってね。とても可愛がってもらいました。もっとも私は、先輩の言うままに、すぐに煮物を作ったり、魚を下ろせたりしましたので、余計に可愛がってもらえたんだと思います。色々教えてもいただきました。私が要領良く仕事をこなすものですから、教えるほうも気持ちが良かったのではないでしょうか」。
可愛がられたといっても、仕事が楽になるわけではない。言い方を替えれば、「これも、あれも」と何倍も働かされたことになる。霜焼けした足で、駆け回る15歳の少年。それは思い描いていた料理人の姿だったのだろうか。
料理人神谷、上京ス。
「先輩達に言われるまま料理を勉強していた頃です。ある日、日本で一番の料理人が、うちの旅館に来てくださったんですね。この人に出会って、料理というのは凄いな、料理人は格好いいなと改めて思いました」。
この日本一の料理人の来訪が、神谷の視界を広げた。京都に出て本格的に日本料理を学んだのも、この人との出会いがあったから。そして21歳になった神谷は、東京へ向かうことになる。修業を開始して6年、年齢は若かったが、いっぱしの料理人である。
「赤坂の『きくみ』という店に行きました。こちらに来ても、休みは全然無かったです(笑)」。
この頃になると師と仰ぐ人もいた。竹内啓恭氏である。竹内氏は、北大路魯山人の下で、煮方を務めた料理人である。
「師匠が作るものは、他とはまるで違って、もうめちゃめちゃ旨いんです。出汁の取り方が違うんですね。その師匠が亡くなる時に、『自分がいなくなったら、食べることが師匠なんだぞ』という言葉を残してくださいました」。
この時、神谷を、師と同じように可愛がってくれていた1人に、「割烹やました」の山下茂氏がいる。山下氏は、竹内氏について次のように述べ、諭している。
「お前の師匠の竹内啓恭氏は関西料理を象徴する店『錦水』に18年間いた。そんな貴重な人はいない。そこの料理をお前は受け継いでいる。だから疎かに料理をするんじゃないよ」と。
この言葉を神谷は今も大事に胸にしまっている。ついでの話であるが、この時、山下氏から、次のようにも言われたそうだ。
「だけど料理をやるばっかりじゃなくて、70、80歳になっても習い事をすること。決して天狗になってはいけない。いくつになっても師をもつことが大切だ」と。
この言葉も大事にし、今も習い事を常に心掛けているそうだ。
「きくみ」の時代。
さて、上京し、赤坂の「きくみ」で働き始めた神谷の料理長時代の話に移ろう。
「当時、女将さんから『飲食店は100ある売上のうち30%が給料で、30%が家賃、残りの30%が後の食材費等で、最後に残った10%が純利益。この10%の利益を目指すんだよ』と教わりました」と神谷。
料理のみに心血を注いできた神谷にとっては新鮮な一言だったに違いない。
30と30と30。そして残りの10。料理人から料理長になるには数字を知らなければならない。女将がわざわざ経営の話をしたのも、料理長としての神谷に対する期待の表れだったかもしれない。
「とにかく、当時はね。3店舗の料理長をしていたから忙しくてしかたなかった。赤坂でしょ。霞ヶ関、それに新宿のお店。駆け回って足が痛くて歩けない。特許庁の前で蹲ったこともありました」。
3店舗を束ね、なおかつ全ての店で利益をだす。当時の給料は100万円。
「『一つの店で30万円。3店舗だから100万円くださいって』、女将に言ったんです」。
太っ腹な女将さんである。神谷の言葉に頷き、100万円を支払った。実際、神谷はそれ以上の仕事をした。
「赤坂はふぐのお店だったんですね。冬はいいけど、夏はだめ。それで夏は氷の彫刻を作ったりしてね。そういうのを始めると、夏でも沢山のお客さんがいらっしゃるようになりました」。
もともと客筋も良かったという。そういうお客さんの相手をするために、カウンターにも出た。
「もともと厨房で育ってきた私だから、お客さんと話すことは無かったし、だいたい面白い話なんて出来ないタチだったんです。お酒もそうは飲めないし。でも、この時は、そうも言っていられないでしょ。だから、ちょっと珍しいお酒を用意しておくんです。ちょっと一杯いかがですか、みたいなね。そういえば、包丁にドライバーをくっつけたこともあったな。ゴルフ好きの人も多いから、『ドライバーを一丁もってこい』なんて言ってね」。
工夫した。努力もした。師匠の言いつけも守って、自腹で食べ歩きもした。繁盛店にも通った。料理長は責任者である。舵を取らなければいけいない。重圧もあったが、それを跳ね返すだけの自信もあった。
「店の設計からメニューまで、全部任せてもらっていましたから」と神谷。ある意味、店主と同じ体験をさせてもらっていたとも言える。
ちなみに、36歳の時に血圧が上がり、上が240、下が120となって倒れたことがあるそうだ。それでも、「俺がやらねば」と、「昼の2時から夜の8時までずっとふぐを捌きっぱなしだった」という。「今でも針やマッサージをしなければならない身体になってしまいました」と笑う。
料理人、神谷の真骨頂は、柔軟な発想。
当時の料理店では、料理長が一番だった。料理長の不正に目をつぶるオーナーも少なからずいたようだ。しかし、「きくみ」で料理長となった神谷は、それまでのしきたりを一切断ち切り、食材の仕入れも全てガラス張りにした。
ホールのクオリティアップにも注力し、料理人も、ホールの担当者も、50%、50%のイーブンの目線で見ることにした。
「ホールと料理が、力を合わせて初めていい店ができる」というのが、神谷の持論である。「料理しかできないのでは困るから」とサービスも、計算もできるように料理人たちを仕込んでいった。
このように、今までの料理人のスタイルを、柔軟な発想で、進化させていく。これが神谷の真骨頂でもある。
「私の兄が、ロンドンにいまして。神谷宗佑というんですが。彼は24歳で渡欧し、スイスの首都ベルンの五つ星ホテル、ベルビュウパレスで本邦初の日本料理を披露しました。ロンドンではHIROKOチェーン板長、総支配人として活躍するのですが、とにかく、サービスの天才だったんです。そういう兄を見ていたもんですから、サービスの重要性も良く分かっていたんです」。
料理人に、自ら作った料理を食べるようにも言った。これも、それまでの習慣を破ったものだ。「良くあるのが、ぱっと味をだいたい確認しただけで、『よし』と決めてしまう。いくら料理人でも、ちゃんと食べないと本当の味は判らないんですよ」。
これも師と仰ぐ竹内氏から教わったこと。
「私が初めて料理長になった時です。『知っていても訊きなさい。良いことは今すぐやって、駄目だと思うことはすぐに辞めなさい』と教わりました。今では私の信念になっています」。
良いか悪いか判断するのは誰でもない、自分である。過去の習慣にとらわれず、「良いと思うことは今すぐやる」、逆に「駄目だと思ったことはすぐに辞める」。
料理ではさらに、この教えが鮮明な形になって現われる。
日本料理だけではなく、様々な料理の良いところを吸収し、アレンジするのもその一つである。「キャビアやフォアグラなど、美味しいと思ったら何でも使っていいと思う」と言っている。
実際、35年前に神谷は初めてフォアグラを知ったそうだ。イタリアンをやっていた友人から学んだそうで、「フォアグラをバターのように調理する様子は目から鱗だった」と語っている。
むろん、すぐに料理に採り入れている。
年齢を重ねた今も好奇心は旺盛で、貪欲だ。海外にも頻繁に出かけ、旨い料理を探し、歩く。「食べることが師匠だ」と言った師の教えを今もしっかり守っている証に他ならない。
頑な信念がある。だからこそ、物事に柔軟に対応することができるのかもしれない。自信のある人が、変わることを恐れないと同じことなのだろう。
思えば、15歳から始まった修業の旅である。わんぱく坊主であった神谷は、料理によって、社会を知り、己を知り、人の温かさを知り、冷たさもまた知ったはずだ。
それでもなお、料理について語る時、神谷はわんぱくだった頃の子供時代に戻ったかのようになった。そこがまたいいのではないだろうか。「元気で活動的な子ども」のように、まさに料理に対して、純粋で、かつ元気で活動的な神谷の姿がそこにはあった。
ちなみに神谷が、独立したのは41歳の時。現在は調理師学校で講師も務め、多方面で活躍されている。
 |
 |
 |
| 14歳の頃。 | 26歳の頃。修行時代。 | 26歳の頃。修行時代。 |
| ツイート |
この企業・代表の方にコンタクトを取りたい方
この企業にご興味のある方、コンタクトを取りたい方、また代表にメッセージを送りたいといった方は、下記フォームよりご登録下さい。当社が連絡を取り、返信させていただきます。
例)テレビ番組用に取材したい、自社の商品をPRしたい、この企業で働いてみたい、中学時代の同級生だった など
